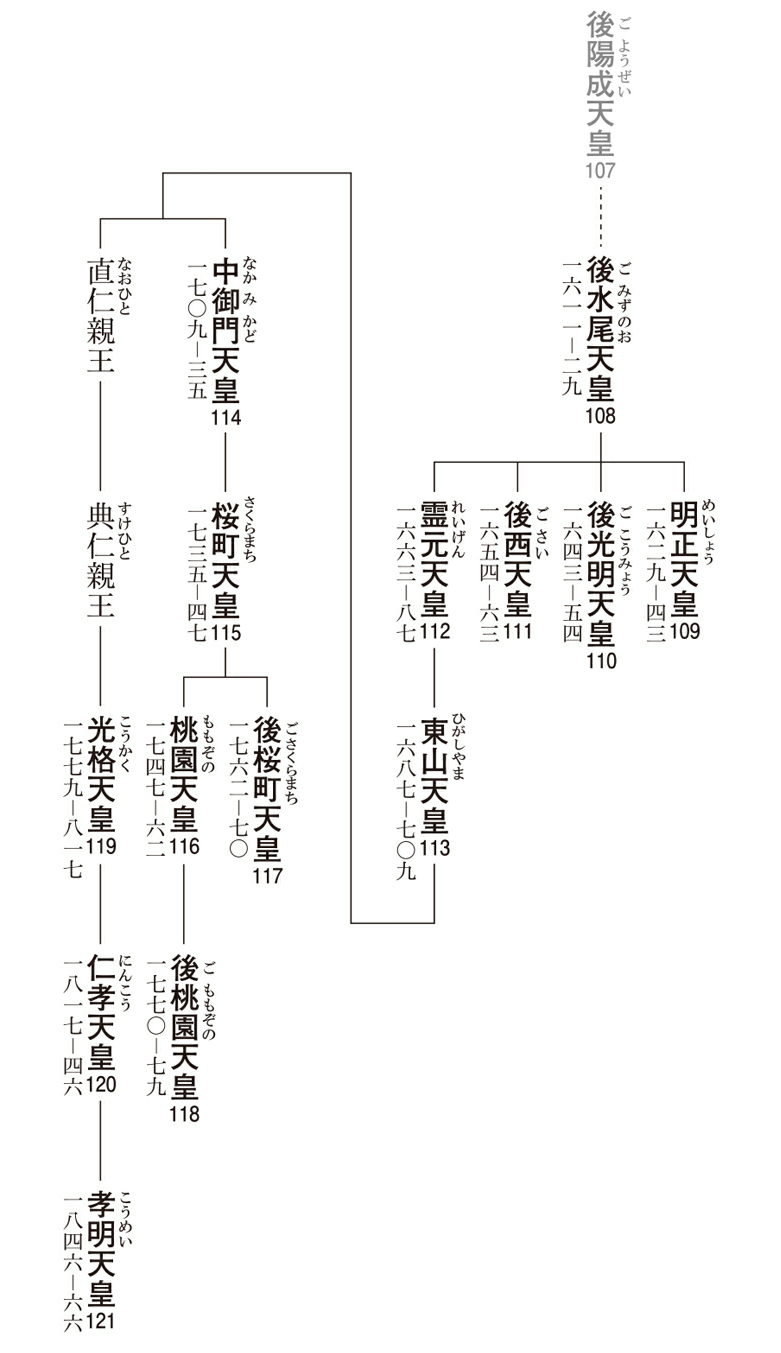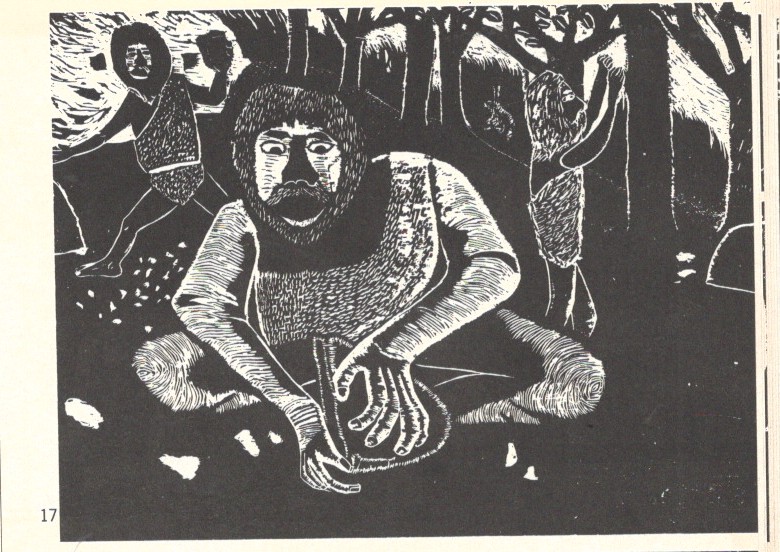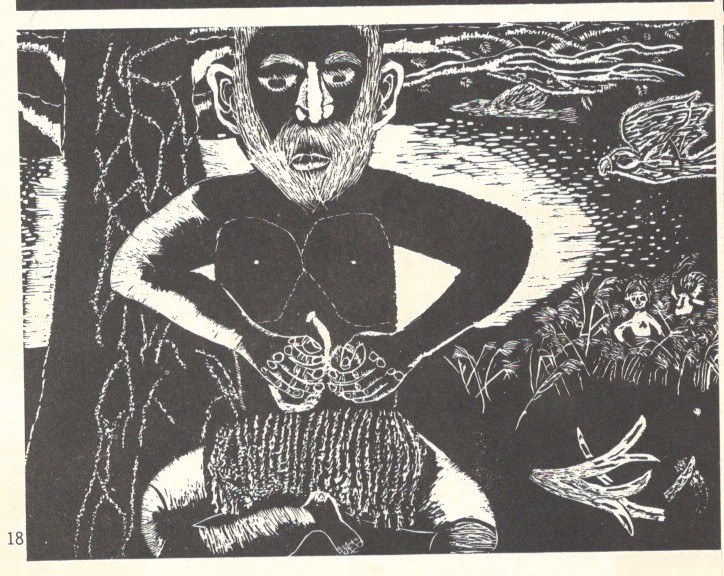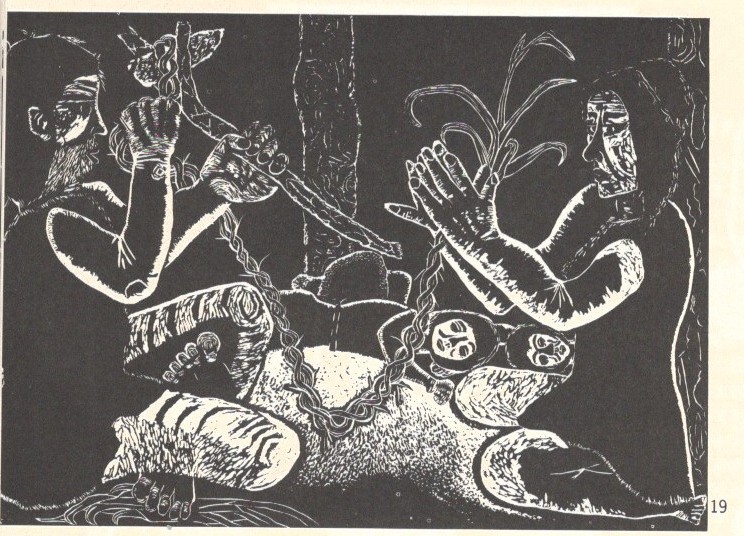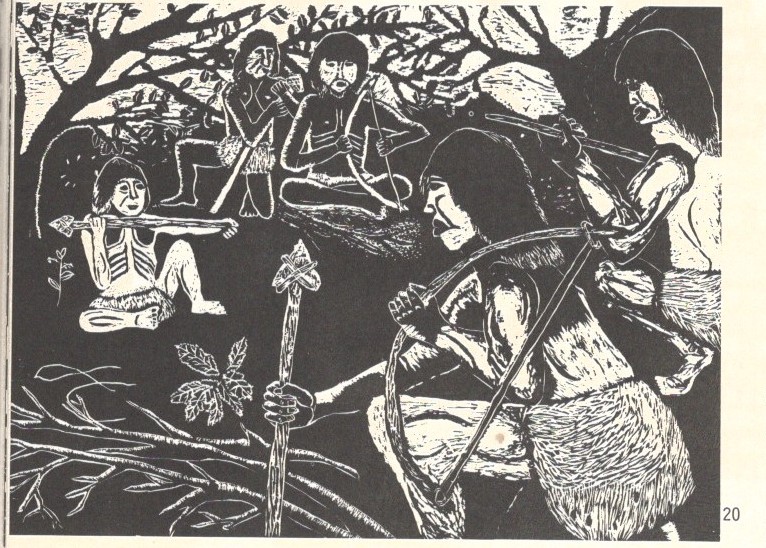ことば日本史シリーズ、江戸時代です
お目見え
将軍に直接会うことができる、つまり将軍から見える立場の人の身分を「御目見(おめみえ)」といった。
平安末期から、武家社会で主従関係をむすぶために従者となる者が主人に謁見する儀式は「見参」と呼ばれていたが、
安土桃山時代に「御目見」というようになり、
江戸幕府にいたってその言葉が幕臣の格式をも示すものとなった。
御目見することには、将軍との君臣関係を確認するという意味があったが、
御目見以上であるか以下であるかによって、家格はまったく違ってしまう。
御目見以上は、一万石以上なら大名、
一万石以下なら旗本。
御目見以下は御家人である。
この武家社会の制度をふまえて、
一般町家でも奉公人が奉公に入る前に、
まず主人に御目見して、試傭期間である「御目見奉公」をするということが行われるようになる。
こうしたことから、やがて身分の高い人に会うことを一般に、御目見というようにもなった
もう一つのお目見え
この言葉は演劇分野にも転用された
特に江戸時代の歌舞伎界で役者が名題(なだい)に昇進し、
初めて大役を担って観客の前に立つ時、
それを「お目見え」と称して特別な扱いをするようになったのです。
この慣習は、歌舞伎だけでなく文楽、能、さらには落語や講談など、広く伝統芸能に継承されました。
お目見えには、その人物の将来を占う意味や、
芸の成熟度を世間に示す目的が含まれており、
観客との初対面という以上の象徴的価値がありました。
明治期以降、西洋演劇が導入されるなかでも「お目見え」という表現は日本独自の舞台文化として残り、
俳優の初出演や新作舞台の発表などに使用され続けています。
特に、俳優や劇団が「本格的な商業舞台にデビューする」瞬間は、今なお「お目見え」として記録されることが多くあります。