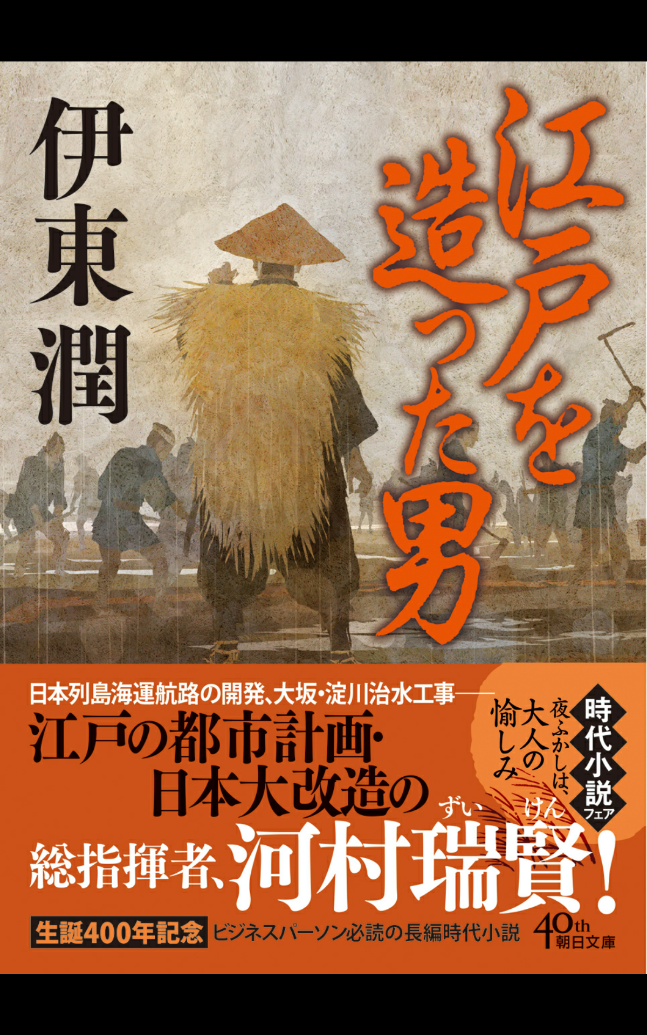[河村瑞賢]1 江戸へ
の続きです
旅立ち?
江戸の口入屋で一生懸命頑張って、信頼も勝ち取ってこれからという時に、主人が亡くなり職を失う
次に進むべき道が定まらず、蓄えも尽きて、その日の稼ぎのため、車力となる
精神的にも追い込まれていく
そんな時、大阪で、23歳で後家になった女性が、こぼれ米を拾うところから、苦労して商売を広げ
屈指の両替商になったという話を聞いた
よし、大阪に行こう
身支度を整え、大阪に向かう
1日目、平塚に泊まり、翌日、酒匂川にさしかかる
川を渡ろうとして中ほどで躓いてしまい、激痛が走る
親指の爪が剥がれてしまっていた
手拭いを親指に巻くがとても歩けたものではない
旅の始めに幸先が悪いこと
途方に暮れていると、老人が通りかかった
どうした
膏薬を塗ってくれた
傷が癒えるまで、小田原に逗留するがいい
ありがとうございます
しばらく休んだあと、立ち上がろうとすると紙入れが落ちている
持ち上げるとずしりと重い
さっきのお年寄りが落としたものか
探し回ったが見つからない
そうこうしているうちに、男に絡まれる
すったもんだしているうちに、紙入れが落ちる
俺の紙入れを盗みやがったな
これは、先程拾ったもので。。
大騒ぎになって人だかり
そこに、先程の老人が来て、紙入れの主が証明される
そんな縁で、老人と懇意になる
君は万人に一人の骨相をしている。きっと天下を驚かすようなことをする
どこへ行くんだい
大阪です
大阪かぁ
いけませんか
大阪でもそこそこは成功するだろうがな
江戸で事を成すべきだ。
骨相にそう書いてある
己一個の欲心を捨て、万民に尽くす気持ちを持てば、
天地の雲気がすべて味方し、将軍でさえ感謝する仕事ができる
老人とは別れたが、言葉が胸に突き刺さる
思えば、旅の始めに怪我をしたのも、江戸に戻れという天の啓示かもしれない
再びの江戸
江戸に戻る
とはいえ、元々行き詰まったから大阪に行こうとした
どうにも居場所がない
いっそのこと身を投げるか
ぼんやりと川を眺めていると
目黒川の上流から何かが流れてきていることに気がついた
茄子やきゅうり
ちょうど七月の盂蘭盆(うらぼん)の時で、精霊棚に飾られていたのが捨てられて流れてきていた
腹減った
拾って食べてみたら
あまりの塩辛さに吐き出す
海に浸かっていたため塩味が染み込んでいた
待てよ
このままじゃ売れないけど、漬物にしてみたら
なけなしの金で桶を買い
漬物にしてみた
こいつはいける
直感がそう告げた
浜にいた物乞いたちに、流れている野菜を集めてくるよう頼む
たちまちかなりの量の漬物が出来上がった
どこで売ろう
宿とかでは、今でも誰かが取引している
今まで漬物を売っていないところ
そうだ!普請の現場だ
疲れ切っている彼らは、休み時間に漬物屋まで買いに行ったりしない
日々の仕事で塩気を欲している
漬物を小分けにして、笹の葉でくるんだ
おこうこはいらんかね。紀州のおこうこはいらんかね
試し食いとして、ただで一切れを与えたので
みんな安心して買っていった
小分けにしたのも当たった
漬物屋はある程度まとまった量でしか売らない
そうか。
商いとは人のしないことをし、人の望む物を望む形で供することなのだ
ただ瓜や茄子を集めて売るだけでは、人は金を払わない。
そこに何らかの値打ちを付けるから金を払うのだ
野菜を集めてくれた物乞いの少年の寅吉と
ひたすら漬物を作った
盂蘭盆が過ぎるともう野菜は流れてこなかったが
売り上げた金でまた仕入れる事が出来た
七兵衛の紀州漬けは人足たちの間で広まっていった
続きはシリーズの次回ね
[人物]シリーズはこちら(少し下げてね)