[日本語の発音] 奈良時代に母音は8個あった
[日本語の発音] ハヒフヘホはパピプペポ
[日本語の発音] 発音通りに書いた時代
[日本語の発音] ゐ、ゑ、を
[日本語の発音] 漢字仮名混じり文の開発
の続きです
室町時代
室町時代になります
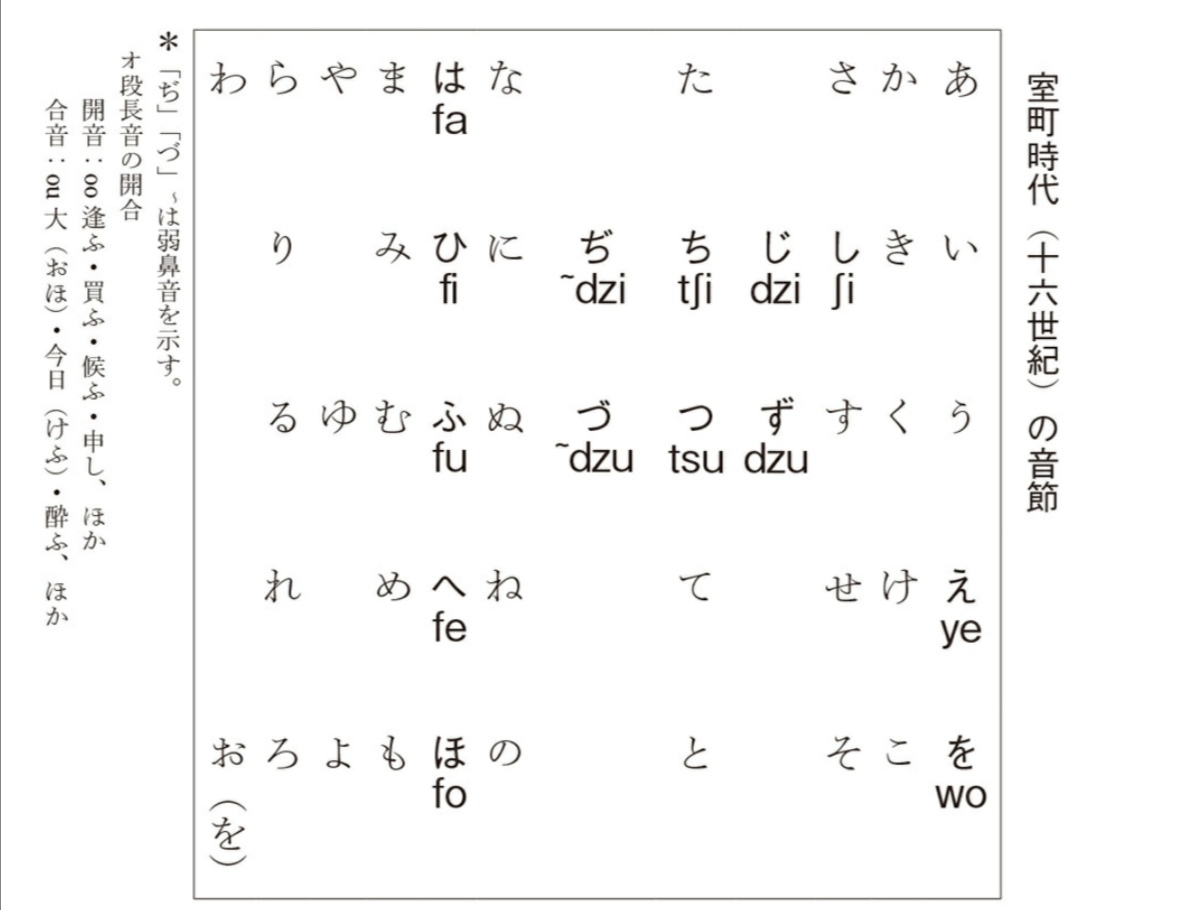
室町時代の日本語の発音を調べるにおいて、重要かつ正確な資料が出現します
宣教師の作った辞書です
イエズス会のポルトガル人のロドリゲスが日本語を詳細に調べ
習得すべく辞書を作った
日本語のかなは音節単位で一文字だから
途中で実際の発音が変化していても気づきにくい
西洋の辞書が存在すると、母音と子音に分けて表記してくれるから
当時、どういう発音をしていたかが明確に分かる
『日葡辞書』では、「羽柴秀吉」の発音は、「ファシバフィデヨシ」だったということが分かる
四つ仮名混同
これを踏まえて、室町時代に起きた日本語の発音の変化をみると
「四つ仮名混同」ということがある
鎌倉時代以前の仮名の用法によれば、「藤」は「ふぢ」、「富士」は「ふじ」で区別された。
その発音「藤(ふぢfudi)/富士(ふじfuzi)」が違っていたのである。
同じように、「楫(かぢkadi)/家事(かじkazi)」、
「屑(くづkudu)/葛(くずkuzu)」なども同じく発音が違っていた
ところが室町時代の中頃に
「じ」「ぢ」の音が[dzi]の音として合流し、
「ず」「づ」の音が[dzu]の音として合流する
となると、仮名遣いの問題が発生する。
仮名遣いとは、前回もお話しした、同じ発音なのに、
文字をどっち使って良いか分からず困ってしまう問題
「じ/ぢ」「ず/づ」の仮名遣いを「四つ仮名」という。
仮名の使い分けは、現代仮名遣いにも影を落としている。
日本語ワープロで入力する時、毎回迷う
地面の地って、地(ち)にてんてんなのに、なんで「ぢめん」で変換してくれずに「じめん」なのか
毎回おかしいなあ、と思っている
四つ仮名混同の問題は、前回お話しした仮名遣いの創始者藤原定家のころ(鎌倉時代)にもなかった問題
その頃は「藤(ふぢfudi)」と「富士(ふじfuzi)」では発音が異なっていた
四つ仮名混同といわれる変化が生じる前に、先駆けとなるタ行「ち・つ」の子音変化が起こり
引きずられて、「じ/ぢ」「ず/づ」が同じ音になってしまった
厳密に言うと、室町時代ではほぼ一緒
完全に同じ音になったのは、江戸時代の元禄の頃になる
江戸時代の古典学者の契沖はこれを指摘し、田舎の人は一緒だが、
都の人は注意して鼻にかけて発音すれば可能だとしている
現在において「じ/ぢ/ず/づ」の4音全てが同じ音で発音される地域がある
東北地方の大部分と山陰地方の一部
いわゆるズーズー弁である